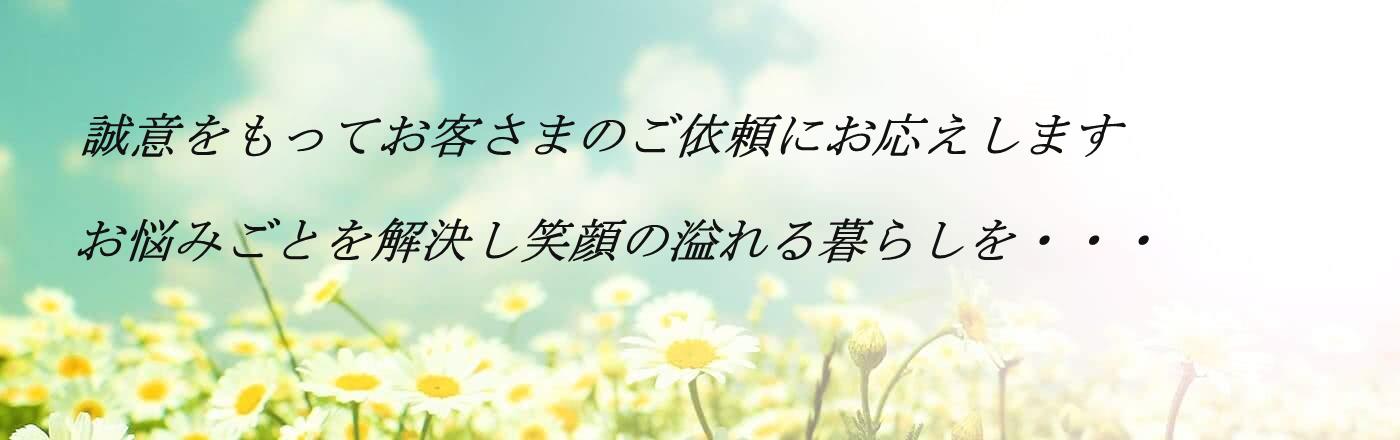
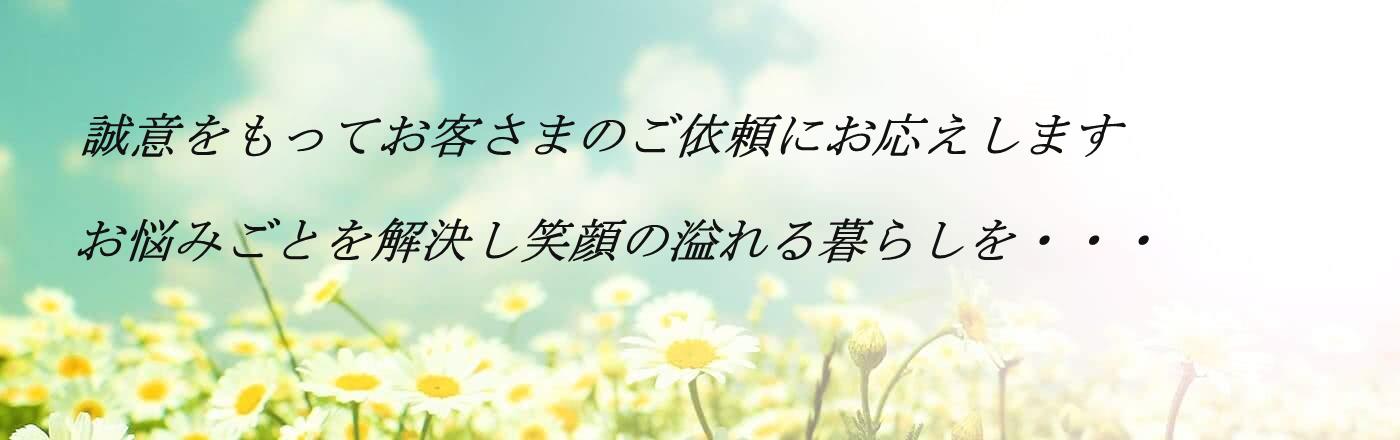
-遺言書の種類-
遺言書の種類として、実際によく活用されている「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
自筆証書遺言とは
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成する遺言。
メリット
・手軽に作成できる。
・費用がかからない。
デメリット
・文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある。
・遺言の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。
・家庭裁判所の検認手続が必要である。
・発見してもらえないおそれがある。
自筆証書遺言の流れ
①必要となる道具を準備する。(紙、封筒、ペン、印鑑および預金通帳等の相続財産の資料)
②以下のルールを厳守して記述する。
・財産目録以外は、全て本人が手書きで書く。(パソコンの使用は不可)
・作成した日付を書く。(年月日まできちんと書く・・吉日等は不可)
・氏名を書く
・印鑑を押す
③封筒に入れ、遺言書に押した印鑑を使用して封印する。
④保管する。
誰でもすぐに手にすることができる場所だと内容を見られてしまう可能性がありますが、極端に分からない場所では相続時に誰にも見つけられないということもあります。
公正証書遺言とは
遺言者が、原則として、証人 2 人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成する遺言。
メリット
・遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
・原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
・家庭裁判所による検認手続が不要である。
デメリット
・作成までに手間がかかる。
・公証人以外に証人を2人以上用意しなければならない。
・費用がかかる。(下表のとおり公証人手数料は必要となる。また、証人においても自分で2人を手配する場合には費用はかかりませんが、公証役場で紹介を受ける場合には、1人につき5,000円~15,000円程度必要)
(公証人手数料令第9条別表)出典:日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
具体的な手数料算出の留意点
上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、次の点に留意が必要です。
⑴ 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
⑵ 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。
⑶ さらに、遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
すなわち、原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
⑷ 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50 %加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
公正証書遺言の流れ
①遺言書の内容を整理する。
②証人を用意する。
③必要書類を準備する。
④公証役場で遺言書を作成する。
⑤遺言書の原本は公証役場に保管されます。同時に正本と謄本が本人に交付されます。
必要な書類
・遺言者の戸籍謄本
・遺言者と財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に譲る場合は、その人の住民票の写し
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
・預貯金の通帳のコピー。銀行の場合、銀行名、支店名、種別、口座番号、残高。ゆうちょ銀行では、記号、番号、種別、残高
・証人を知人に依頼する際には、その人の名前、住所、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)
・遺言執行者を指定する場合は、その方の名前、住所、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)
(相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要)
・発行から3か月以内の印鑑登録証明書。印鑑登録をしていない場合は運転免許証やパスポート
・遺言者の実印(印鑑登録していない場合は、認印)、証人の認印が必要
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言。
メリット
・自筆証書遺言のように手書きである必要はなくワープロで作成してもかまわない。
・自分で用意した遺言に封をした状態で公証役場に持っていきますから、遺言の中身が他人に知られることが無い。
・相続人は亡くなった人が遺言を残しているかどうかわからない時は、公証役場に問い合わせれば遺言の有無が確認できる。
(存在するとの回答があれば、自宅等の保管してありそうな場所を探します)
・秘密証書遺言の1番のメリットは遺言の内容を第三者に知られることなく、かつ遺言が作成者本人によって作られたことを証明できることと言えます。
デメリット
・遺言自体は本人が保管をし公証人は保管しないので、作成した遺言が発見されない危険性がある。
・申述時に証人2人以上が必要です。
・費用は公証役場手数料として定額で1万1000円が必要です。
・遺言の検認のため家庭裁判所に請求が必要です。
秘密証書遺言の流れ
①遺言の本文を作成する。
②遺言に封をする。(遺言で用いた印で封印する)
③公証役場へ持参し手続きをする。(公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言であること、氏名住所を申述)
④遺言を持ち帰り、自分で保管する。
※新たに自筆証書遺言の法務局保管制度が開始されたことにより秘密証書遺言のメリットが弱まり、秘密証書遺言を選択される方は少ない状況です。
自筆証書遺言の法務局保管制度とは
自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かり,その原本及びデータを長期間適正に管理される制度。
戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、又は関係相続人等が、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたとき関係相続人等に対して、遺言書保管官が、遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせします。
メリット
・法務局で形式面の確認があり間違いを指摘してもらうことができる。
・法務局の保管によって破棄,隠匿,改ざん等を防ぐ。
・遺言書の紛失・亡失のおそれがない。
・死亡時に遺言の存在が相続人に通知されるため遺言の存在が明らかになる。
(保管申請時には、別段、ご家族などには通知はされません)
・家庭裁判所の検認が不要です。
・公正証書遺言に比べて、公証人に支払う手数料が安い。(保管年数に関係なく申請時に定額、3900円/遺言書1通)
デメリット
・決められた様式で遺言書を作成する必要がある。
(余白:必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保)
・形式のみのチェックであり、遺言の内容か否かまではチェックされないため文意不明等により無効となるおそれがある。
・代理人ではなく本人が法務局に行く必要がある。
保管申請の流れ
①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する。
②保管の申請をする遺言書保管所を決める。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所
③申請書を作成する・・様式は,法務省 HPからダウンロードできます。
④保管の申請の予約をする。
⑤保管の申請をする・・遺言書、保管申請書、本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書、手数料を用意する。
⑥保管証を受け取る。
まとめ
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 作成者 | 本人 | 公証人 | 本人 |
| 証人の要否 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 保管方法 | 本人 | 公証役場 | 本人 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要※⑴ | 不要 | 必要※⑴ |
| 偽造などの危険度 | あり | なし | ややあり |
| 秘密性 | 存在の有無を秘密にできる | 公証人や証人から遺言公正証書を作成したことや遺言の内容が漏れることはない | 内容のみ秘密 |
| 費用 | ほとんど不要 |
公証役場手数料 |
公証役場手数料 |
※⑴ 検認の申立ては遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分、検認証明書は収入印紙150円分です。その他、家庭裁判所との連絡用に郵便切手が別途必要となります。
上記のように各遺言書においてはメリットとデメリットがありますが、ご自身のその時の状況にあわせてふさわしい形を選ぶようにしましょう。
また、自筆証書遺言を書かれる方には誰にも相談されずに遺言書を遺されることが多いです。
専門家に相談されずに書かれた自筆証書遺言は、ご自身の思い込みにより間違った書き方をされている場合があり、結局使えないことがあります。
かけがえのない方への想いを成就させるためにも、自筆証書遺言は専門家による内容のチェックをお勧めします。
ご相談をご希望のお客様はあらかじめこちらのお問い合わせフォームよりご予約ください。
お問い合わせ